“Asymptomatic torus mandibularis”というタイトルのcase reportがAJMからPublishされました。
Acceptに至るまで2年以上にわたりReject6回+Revision1回を経験し、まさに七転び八起きで多くを学びました。
Asymptomatic torus mandibularis
Torus mandibularis (TM)とは
TMは日本語で下顎隆起と呼ばれ、その本態は下顎骨に生じる良性腫瘍である骨軟骨腫 (exostosis)です。上顎骨に生じると口蓋隆起(torus palatinus)という名前になります。
全く別の疾患で入院されていた患者さんの口腔内診察時に所見を見つけたものの、見慣れない口腔内病変でうまくsearch termを設定できず、鑑別に苦慮しました。
歯科の先生にTMの一般論について尋ねたところ
「歯科医にとっては日常的に遭遇するcommon disease、無症状であれば経過観察で問題ない」
と教えてもらい、その後の文献検索で
“The discovery of these exostoses usually occurs incidentally during a routine clinical exam”という全く同様の記述を見つけました。
「歯科医にとってはcommonだが内科医にとってはuncommon」というギャップが興味深く、TMについて内科医向けに教育的な報告ができるのでは、感じたことが執筆のきっかけでした。
執筆プロセス:論文Rejectを再考する
私はPGY7から英文誌に挑戦し始め、この原稿はその初期に執筆開始したうちの一つです。当初150-200wordsの本文を作成して投稿作業を行っていましたが、最初の5誌はすべてeditor kickという厳しい結果でした。
6誌目でなんとかMajor revisionのチャンスをもらったもののあえなくReject、そしてDecision letterに記された辛辣な査読コメントの数々に完全に心が折れ、その後1年間原稿を塩漬けにしていました。
そんなある日、Journal of Hospital MedicineのEditor-in-Chiefの記事を目にしました。
【論文Rejectを再考する】
・著者自身の価値は否定されていない
・陰性感情を処理するため少しだけ時間を置く
・事前に複数の投稿先を用意し,どんどん次へ進む
・査読コメントを参考に原稿修正など,Acceptの過程で避けられないプロセスを乗り越えるためのマインドセットが紹介されています https://t.co/WqFgvUpnol
— Yohei Masuda (@YoheiM_MD) May 1, 2025
内容の多くは執筆経験が豊富な先生方は自然に会得しているでしょうし、成書に記載されていることも多いと思います。自分も周囲から同様のアドバイスを受けてはいたものの、いまいち飲み込めていない部分が多かったのですが、JHMの編集長直伝のメッセージはとてもわかり易く、めちゃくちゃ沁みました。
査読コメントを踏まえた修正を行い次の雑誌に再投稿する
Reject自体は決して嬉しい経験ではありませんが、査読コメント付きのRejectとなった場合には、そのコメントを次の原稿に反映することで必ず原稿の質が改善される、というメッセージです。
これを読んだ後、一念発起してこれまで目を背けていたReject時の査読コメントを読み直し、修正を行うことにしました。
原稿が塩漬けになっている間も「Academic writingについて理解できていない」という自分の課題は明確に感じていました。そこでライティングスキルを向上するべく、「伝わる英文」の修得に取り組みました。また筆頭、共著を含め複数のOriginal article, Case report, Clinical Picture執筆(+最近は査読)に参加する機会を頂き、主観的、客観的に文章を評価する、という場数を踏むことができたのもとても良い経験でした。
これらの経験を踏まえて原稿を見直すと、曖昧で非効果的な文章が多く、パラグラフの構成が稚拙なために主張が適切に伝わっていない、論理が飛躍していると判断されてもおかしくない箇所が複数あることに気づきました。
また、以前は辛辣な言葉と感じた査読コメントも、今読むと「言われてみればそのとおりだ」と感じる妥当な指摘ばかりで、決して悪意ではなく原稿を改善するための建設的なフィードバック、不完全な論理を補うピースを提案していたということを理解することができました。
今回の原稿に関しては、自分の伝えたいメッセージを十分に伝えるためには150-200wordsでは足りないと判断し、650wordsをしっかり使えて教育的な論文を募集しているAJMを次の投稿先に決め、大幅に文章を書き換えました。
AJM
Day 12: Decision letter
Day 13: Published online
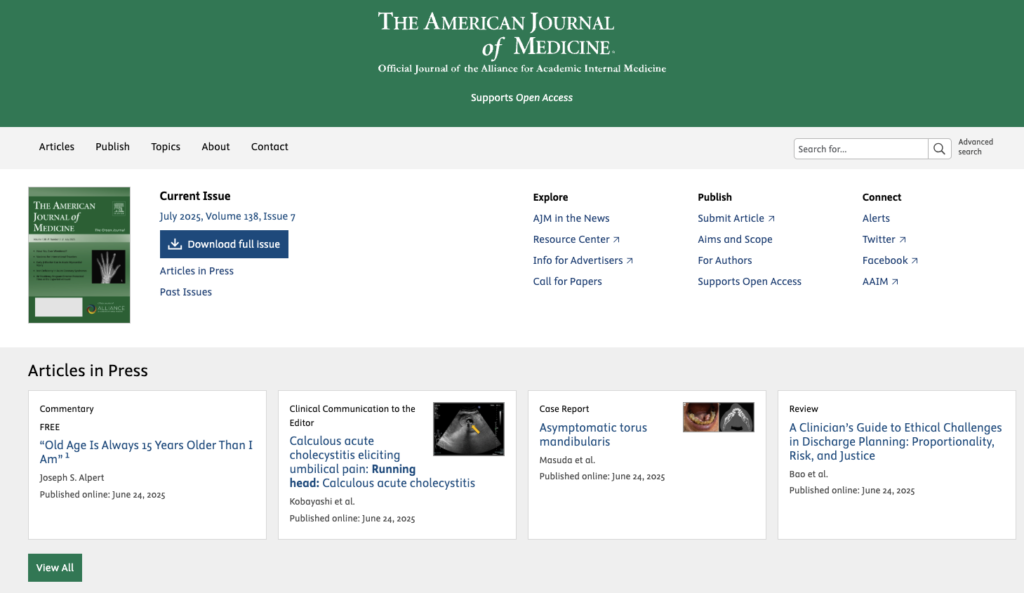
読み慣れたグリーンジャーナルのトップページに自分の論文が掲載されているのは感慨深いものがありました。
おそらく、どんな論文にも掲載先がある


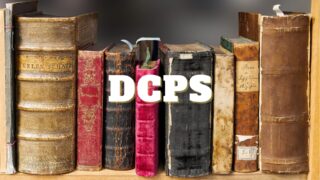
Comments